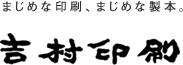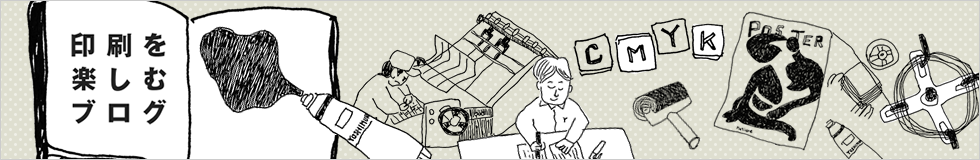「活版印刷を深掘り」の特集も9回目となりました。吉村印刷の先輩方が、数十年前に実際に行なっていたことを、現代の目線で掘り下げてみようという試みでスタートとしたこの特集。かなりマニアックな部分もありますが、現在の組版の基礎になっているものなので、もう少し掘り下げてみようと思います。
今回も「植字」の続きの話を深掘りしますよ。
文章を活字で組んでいく際、単純に本文を流すだけなら簡単なように見えますが、見出しが入ったり、罫線が入ったり、ノンブル(頁番号のこと)がついたり、柱がついたりといろいろな形があるので、とても手間がかかっていました。

植字は、文選が拾った活字を並べ替えながら体裁を整えていきます。本であれば、1頁組むごとに糸でくくり、何頁も組んでいきます。数頁組んでは受け板に移しますが、頁数の多い書籍は、受け板が何枚も積み重ねられ、場所が相当に必要でした。
■活字の差し替え
校正で赤字が入ったときには、差し替えにも細心の注意が必要です。現在でも組版ソフト上での差し替えには注意を払っていますが、活版の場合は、差し替えるための活字を拾うことから始まります。
書籍の場合は、1頁ずつ糸をピンセットで外し、1字の差し替えぐらいなら、前後の約物2つを半角にして入れこんだり、あるいは四分のコミを4カ所に入れて空きを埋めていきます。
それが出来ないときは、段落が変わるところから逆算して、1字ずつ行をくらなければならないので、入れ間違えなどの二次災害にならないように慎重に作業していました。組版ソフト上で自動的にずれていくのとは違い、すべて人の手作業で進めなければなりませんでした。
また、パソコンでは同じものをつくりたいとき、コピーすれば簡単にできますが、活版では、同じものを必要な数だけ組まなくてはいけません。それだけ労力・資材・時間がプラスされるので、当時はとても大変でした。
次回は、罫線を使った伝票の組版について紹介します。