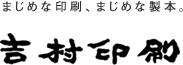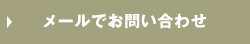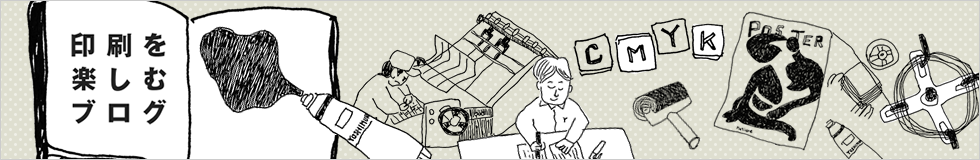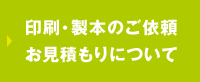暑い季節が終わりを告げ、いよいよ秋も濃くなってきました。秋といえばいろいろありますが、スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋、食欲の秋などが一般的です。
そこで吉村印刷でも秋にふさわしい様々な事柄について、ブログで紹介していきたいと思います。
今回は、古くからある機械で今も現役で使われている、「締め機」について紹介します。

この締め機の年季の入り具合、かなり使い込まれた感じがしませんか? 社内では、「40年近く使っているのでは」といわれています。40年以上勤めている職人に聞いても、導入した時期が分からないほど古い機械です。
締め機とは、製本をするときに紙を締める機械のことです。構造は単純ですが、なくてはならない機械の一つです。
製本するとき、印刷した用紙を4つ折りや8つ折りに折る工程があります。紙を折ってみると分かると思いますが、袋になった部分が膨らみます。そのまま製本工程を進めてしまうと、高さが違ってくるため、積み重ねると不安定になります。折りの後に続く丁合、綴じの作業も、折った部分が膨らんだままではうまくいきません。
ここで締め機の登場です。
板の下に折った紙を積み重ね、大きなねじを回していくと、板が下がって圧力がかかります。そうしてしばらく置くと、空気がぬけ、袋になった部分の膨らみが減ります。

↑がんだれ表紙を締めている様子
こうすることによって、ひと手間かかりますが、丁合・綴じ工程の作業性が向上し仕上がりもよくなります。
普段はなかなか日の目を見ることのない機械ですが、製本工程においてとても重要な役割を担っていることはいうまでもありません。工場の最古参、年齢で言えばおじいちゃんやおばあちゃん世代になりますが、レトロな雰囲気を感じさせてくれるとともに縁の下の力持ちとして今も活躍しています。