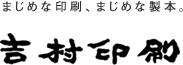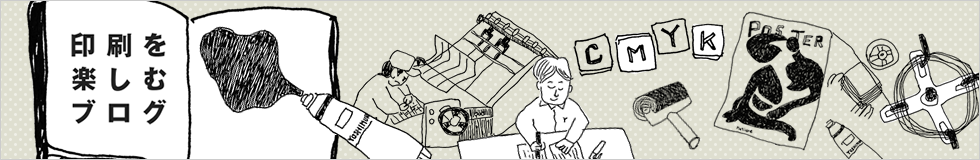福岡の大きな本屋で、「おもしろい本ないかなぁ」と探していたとき、ふと目に留まったのが「築地―鮭屋の小僧が見たこと聞いたこと」という本でした。表紙全体が一目で見えるように置いてあり、著者の自然な表情と「築地」という言葉に強く惹きつけられました。
本文からは、著者の佐藤友美子さんが20代で築地魚河岸の世界に飛び込み、商人や職人、買出人など多くの人から、ありとあらゆる話を聞いてきたこと、途方もない苦労をされながらも楽しく鮭を売っていることがひしひしと伝わってきます。
築地に引き入れてくれた鮭屋の親父、長年帳場を守ってきたきれい好きな女店主、ターレで魚の鮮度を落とさず運ぶ「軽子(かるこ)」、包丁を研いで直してくれた寿司屋の旦那、手間を惜しまず客の望む以上の商品を提供している「築地魚河岸」のスタッフ、滅多に入荷しない口黒マスの情報を教えてくれた同業の仲卸さん。
築地やその界隈で働く人たちと佐藤さんとのありのままの交流が目の前に広がり、本当に築地にいるような気持ちになるんです。
また佐藤さんをはじめとした築地場外の店主たちが、東日本大震災で被災した宮城県や岩手県の漁師、北海道や新潟県の漁師など、全国各地の生産者のもとに赴いていること、実際に魚を獲る現場と密接につながっていることを、この本を読んで初めて知ることができました。
魚が私たちの口に入るまで多くの人たちの手を介していること、魚を知り尽くしたプロ達の丁寧な扱いのおかげで、美味い魚が食べられることを実感しました。
「漁師が命がけで獲った魚を売るからには、一尾たりとも無駄にできまい。お客様である料理人たちだって、命がけで魚を煮たり焼いたり、寿司を握ったりしてるんだから、こちとら、親が死のうが店が火事で燃えようが、一日だって休まないで魚を届けるんだ……。」この言葉に築地のプライドが凝縮されているような気がしています。
築地の歴史を調べて歩いた佐藤さんの苦労は並大抵ではなかったはずと思うと同時に、日本橋から続く魚河岸の歴史を生きてきた生き字引のような方々に、直接話を聞くことができた佐藤さんは、正直うらやましいなと思いました。
この本を読み進めるうちに、私たちも本作りを担う印刷会社として、紙とインキを使いお客様の要望以上の本や印刷物をつくるのが仕事だと、改めて初心に返ることができた気がします。
いつかまた築地に行く機会があれば、必ず鮭屋で鮭を買い、この目でプロの職人の手さばきや立ち振る舞いを見させていただきたいと感じた一冊でした。